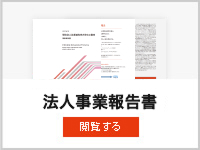一般事業主行動計画の策定について
「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画
職員が仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい職場環境をつくることによって、全ての職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。


2025年4月1日〜2030年3月31日


目標1
所定外労働の削減のための措置継続を図る。
対策
・学校運営に係る制度全般を再点検し、各部署において業務の見直し及び業務量軽減に向けた検討を積極的に推し進める。特に、会議等については、所定勤務時間内での開催やあらかじめ会議終了時刻を設定するなど、効率的な運営に努めるよう周知を図る。(2015年度より継続実施)
・業務のDX化を推進し、作業の効率化や見直しに努める。(2025年度から実施)
・上記の取組等により、月45時間以上の所定外勤務回数を10人以下に減少させる。(2025年度から実施)
【参考1】
2024年度の所定外勤務の平均は15.0時間であった。また、月45時間以上の所定外勤務を行ったのは、33人(管理職を除く延べ人数)であった。
【参考2】
所定外労働時間の推移【2024年度】
(単位:時間)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 25.5 | 18.0 | 15.8 | 15.7 | 11.7 | 13.1 | 12.9 | 15.1 | 11.2 | 12.0 | 17.5 | 20.3 |
目標2
次世代を担う教職員の多様なキャリアデザインを支援する。
対策
・職種ごとに適した勤務制度を導入し、より柔軟な働き方ができるよう整備する。 (2025年度から実施)
・自己研鑽の啓発や資格取得を促進する。(2025年度から実施)
目標3
年次有給休暇の取得促進を図る。
対策
・年次有給休暇の年間取得状況を調査し、結果を公表する。(2015年度より継続実施)
・半年に一度、取得率の低い職員へ年次有給休暇取得の啓発を図る。(2020年度より継続実施)
・連続した年次有給休暇の取得促進の周知を行う。(2025年度から実施)
目標4
男女共に教職員が積極的に育児や介護に参加できる環境を整備する。
対策
・各種休業を取得することへの理解及び制度や給付等に関する周知を推進し、休業の取得しやすさの向上を図る。(2025年度から実施)
・育児や介護における支援制度のさらなる拡充を図る。(2025年度から実施)
・男性教職員の育児休業取得率を40%に引き上げる。(2025年度から実施)
【参考】2024年度 男性の育児休業取得率(※)
直近3年(2022年度から2024年度)の取得実績:33%
※配偶者が出産することを申し出た男性教職員のうち、育児休業等を取得した割合

「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画
女性職員が、仕事と生活の調和を図りながらそれぞれの働く場面において十分な力を発揮できる職場環境を整備し、各部署のリーダーとして活躍する女性職員を増やすため、次の行動計画を策定する。
1.計画期間

2021年4月1日~2026年3月31日
2. 課題

(1)管理職に占める女性職員の割合が低い
管理職に占める女性職員の割合(2020年4月現在)
| 教育職員 | 事務職員 | 薬局職員 | 合計 | ||||
| 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 15.6% | 84.4% | 3.4% | 96.6% | 0.0% | 100.0% | 9.7% | 90.3% |
(2)事務職員における男女の平均継続勤務年数の差が大きい
平均勤続年数(2020年4月現在)
| 教育職員 | 事務職員 | 薬局職員 | 合計 | ||||||||
| 女性 | 男性 | 全体 | 女性 | 男性 | 全体 | 女性 | 男性 | 全体 | 女性 | 男性 | 全体 |
| 11.3年 (-1.8年) |
13.6年 (0.5年) |
13.1年 | 10.6年 (-6.2年) |
20.0年 (3.2年) |
16.8年 | 8.0年 (-0.1年) |
8.3年 (0.2年) |
8.1年 | 10.9年 (-3.2年) |
15.1年 (1.0年) |
14.1年 |
( )内は全体との差
3. 目標

(1)事務職員管理職における女性の割合10%以上を目指す
(2)女性事務職員の平均勤続年数と事務職員全体の平均勤続年数との差を△5年に縮める
4. 取組内容と実施時期

(1)女性事務職員に占める管理職候補者(主任および課長補佐)の割合(現在17.5%)を約30%に引き上げたうえで、女性管理職(課長以上)の数を増やす(2025年度)
(2)女性事務職員のキャリア形成支援を推し進める(2021年度~)
(3)管理職に対する部下の育成に関する意識啓発を行う(2021年度~)
(4)教員の管理職および校務役職者に占める女性の割合を維持する(2021年度~)
(5)所定外労働削減と年次有給休暇の取得促進のため、管理職に対するワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発を行う(2021年度~)
5. 公表数値

(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
事務職員における係長級(主任および課長補佐)に占める女性労働者の割合 44.1% (2024年度)
※自校限定職員を除く。
(2)職業生活と家庭生活の両立に関する雇用環境の整備に関する実績
男女の平均勤続年数の差異 1.98年
男性:13.40年 女性:11.42年 (2025年4月現在)※自校限定職員を除く。
(3)男女の賃金の差異
公表日:2025年6月1日
| 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|
| 全労働者 | 74.0% |
| 正規雇用者 | 88.8% |
| 非正規雇用者 | 135.4% |
対象期間:2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日まで)
賃金:基本給、扶養手当、通勤手当、時間外手当、特殊勤務手当などの各種手当を含み、退職手当は除く。
正規雇用者:出向者については、他社から当社への出向者を含む。
非正規雇用:派遣社員、日雇いを除く。非常勤教員、契約職員、臨時職員、学生アルバイトなどの有期雇用者。
※人員数については、一人あたり賃金の支払の発生した月数を12で除算して換算している。
差異についての補足説明:
<正規労働者>
正規労働者のうち、最も差異が生じているのは事務職員で、男女の賃金の差異は86.8%である。
これは、男性の方が勤続年数が約5年ほど長いことや、管理職における女性の割合が少ないことなどが要因として考えられる。
しかしながら、昨年と比較すると賃金差は改善されている(昨年:82.0%)ため、引き続き一般事業主行動計画に基づき、差異を埋める方策を推進していく。
<非正規労働者>
非正規労働者のうち、賃金の高い契約職員、実習インストラクターといった職種において女性の割合が高いため、女性の平均賃金が男性を上回っている。

その他の情報公表について
「育児・介護休業法」に基づく情報公表
育児・介護休業法に基づき、男性労働者の育児休業等の取得状況を以下のとおり公表します。
育児休業等の取得割合(2024年度)
| 人数 | |
| 配偶者が出産した者の数 | 10 |
| 育児休業を取得した男性数 | 4 |
| 育児休業等の取得割合 | 40.0% |
公表日:2025年6月1日